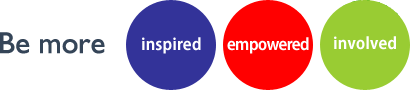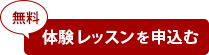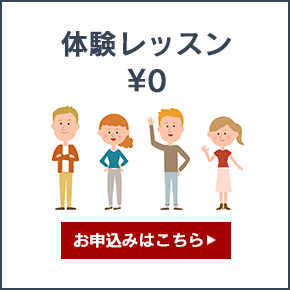英訳・和訳の仕方(大学受験)
投稿日:2025/11/17
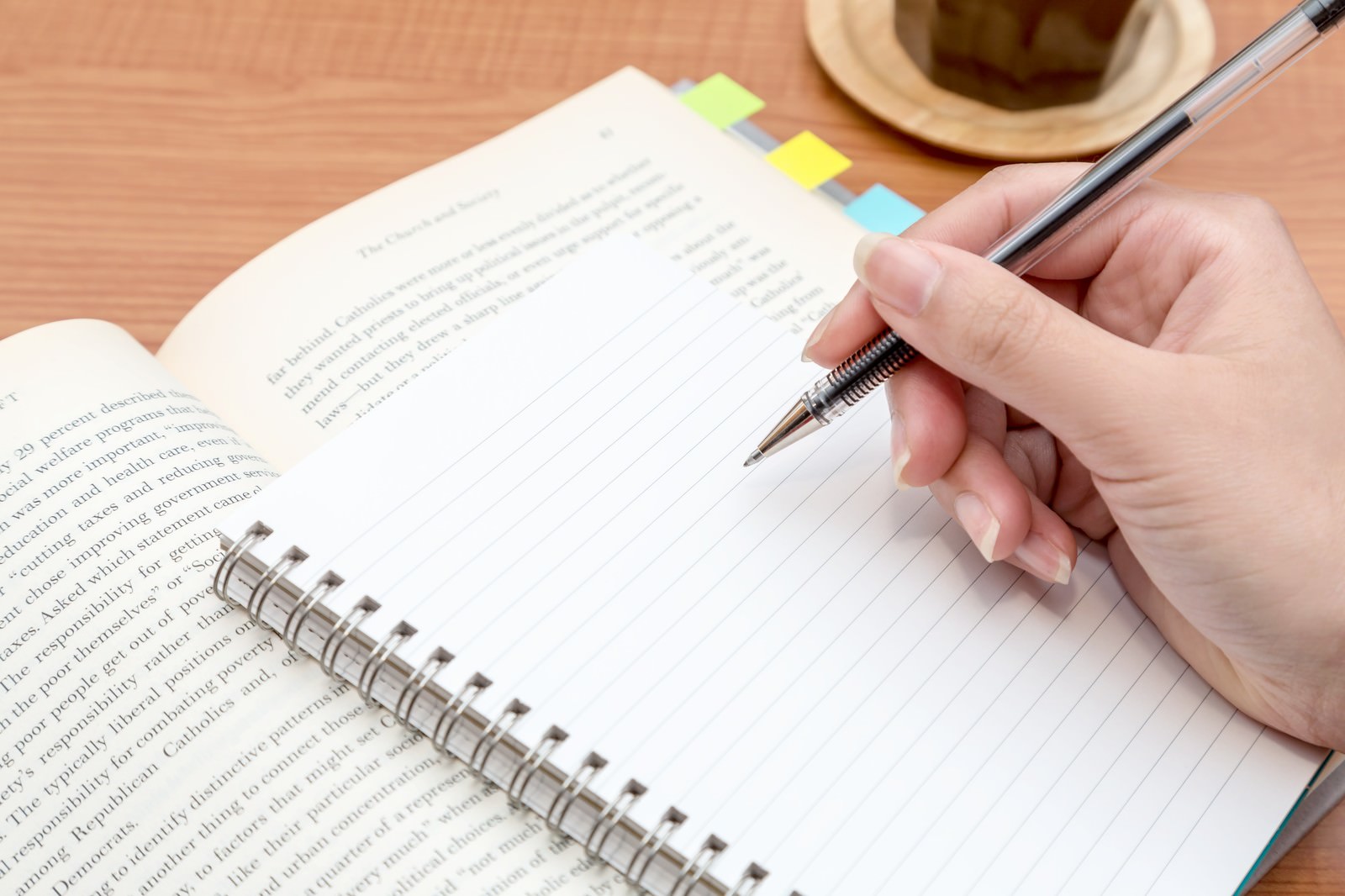
大学受験において、英訳・和訳の問題が出てくると思います。
場合によっては、それが試験の大半か、大半でなくとも配点の比重が高いことがあるでしょう。
お金もらって翻訳(日英、英日両方かつ家族もプロの翻訳者)していた、そして会社勤めの際も業務として新製品取扱説明書や保守マニュアルほか技術文書の翻訳をしていた筆者が、肝を御伝えします。
細かいところを抜きにして、下記3点に気を付けてください。
・書いていないことは書いていけない。
・直訳しない。
・切るところは明確に。
この三つです。
まず、「書いていないことは書いていけない」です。
翻訳の世界には原則があります。それは、「ソースに忠実に」ということです。
ソースはSource(源の意味)です。要するに原文のことです。
原文に書かれていないことは書いてはいけません。
次に、「直訳しない」ことです。
前文と矛盾するようですが、矛盾はしていません。
書いていないことは書かないが、日本語として成り立たせる(直訳でない)ということです。
直訳を良しとしていたら、ただ単語の意味を並べるだけで採点対象となってしまいます。
意訳は必要です。しかし、同時に大幅に外れないよう気を付けてください。
最後に「切るところは明確に」です。
仮に原文が1文になっていても、意味が違わず、読みやすくなるなら、2文にしても良いです。
切る場所はandなどがあります。
やってはいけないことは、訳する箇所が行ったり来たりすることです。
基本的には英文は電車の連結のようになっており、先頭車両、二両目、三両目・・・とぶつ切りに訳していくと意味が通るようになっています。
これを先頭車両、4両目、2両目と訳すとかなりの確率で訳を間違えます。
実務の翻訳と試験問題の訳文の採点は違うとは思っておりません。
生徒さんが書く翻訳文を読んでいて、筆者の実経験と対比した場合に感じた結論を書きました。
なお、赤本などが提示する模範解答は参照しますが、同時にGoogle翻訳も確認します。
そして、筆者自身も生徒さんと一緒に翻訳します。
生徒さんの翻訳、筆者の翻訳、模範解答の訳、Google翻訳を比較するとかなり勉強になります。